|
八木用水路
記念碑 |
 |
佐東地域から祇園方面にかけては太田川の流れより位置が高く、昔から慢性的な水不足で悩まされていた 。大工であった桑原卯之助が 1768年(明和5年)上流より水を引くことを考えて用水路を開きこれ以降水の安定供給がなされ稲作等農業の発展に大きく寄与した。全長16kmに及ぶこの水路は現在に残る歴史的遺産となっている。
太田川橋近くの細野神社下にはこの事業をたたえる記念碑が建てられている。2014年夏の集中豪雨による土砂災害で流されたが2017年2月に復旧された。
|
|
八木用水路 |
 |
高瀬堰の記念碑
「大禹謨]
(だいうぼ)
正面の碑銘 |
 |
旧佐東町一帯は、大雨が降ると太田川の堤防が決壊して大きな被害をうけることが多かった。洪水対策として高瀬堰を固定堰から可働堰にする改良工事が1975年(昭和50年)に完成した。
大禹謨(だいうぼ)碑は中国古代の夏王朝の禹王(うおう)が黄河の水を治めて、治水の神と崇められたのにあやかり、困難な治水事業の完成を願い、今後の安全を祈るため1972年(昭和47年)当時の池田早人町長によって高瀬堰の西岸に建立された。このような禹王ゆかりの碑は全国各地で発見されている |
「大禹謨」の
背面の碑文 |
 |
古川改修工事
記念碑 |
 |
昔、太田川の本流であった古川は、度重なる洪水の歴史を経て1980年(昭和55年)頃より大規模な改修工事が行われ、せせらぎ河川公園として生まれ変わり、地域住民の散策と憩いの場所となっている。 「梅林」の名の由来の梅の木も年々増えてきており、水鳥など野鳥も多く見られ、四季それぞれに趣のある風景を楽しむことができる。
川辺にホタルの里を蘇らせようと、2005年(平成17年)から幼虫の放流が進められ、毎年ホタルを鑑賞する会も行われている。 |
| 古川沿い周辺 |
 |
|
宇那木山
第二号古墳
|
 |
佐東地域では細迫遺跡など、太田川下流域で弥生時代の貝塚が多く見つかっている。
2002年から2003年(平成14~15年)にかけて、緑井の丘陵地に宇那木山第二号古墳として古墳時代初期のものとされている竪穴式石槨が発掘された。 副葬品として珠文鏡・鉄製の槍などが見つかっている。 なかでも中国から伝わった画文帯神獣鏡が出土したことで知られている。この地方では最古の前方後円墳といわれている。
|
| 出土品展示 |
 |
|
広島菜漬 |
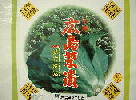 |
川内の農家の木原才治が京都から多葉性の珍菜を持ち帰り、1890年(明治23年)代、在来種の京菜と混植交配を重ね品種固定を図ったので、「広島菜」としてこの地区で普及し現在も盛んに作られている。
食通には特に霜雪に耐えた冬越しの漬物は断然人気がある。
|
| 栽培風景 |
 |
|
JR可部線
緑井駅付近
|
 |
この地域は広島市のベットタウンとして急速に都市化 が進展している。 山陽自動車道広島インターチェンジ周辺の交通の利便性を生かし、緑井駅周辺地区市街地再開発事業の推進により都市機能を集積し、郊外型商業地域とあわせ文化的で魅力ある都市空間の形成が着々となされている。
緑井駅前には、2005年(平成17年)に地域のまちづくりの拠点として、「緑井駅前サロン」が開設された。 障害者や高齢者など歩行困難な方への電動スクーターの無料貸出しを中心に、談話室、まちの情報ステーション、相談ごとの受付などさまざまな利用が期待されている。
|
| 緑井駅前サロン |
 |
|
毘沙門堂山門
|
 |
古くより特に商い人からの信仰を集めており、四天王の中の多聞天(毘沙門天)を祀っている。戦国時代には銀山城(武田山)の北方の守護神でもあった。本堂は1988年(昭和63年)に焼失したが 、1990年(平成2年)に再建された。旧暦正月の初寅祭には県内外より多くの参拝客が集まり大変賑わう。
2014年8月、大雨による土砂災害のため本堂が傾くなどの被害を受けたが2017年に修復された。
本堂の左手の道を少し登ると展望の良い地に多宝塔がある。 |
|
毘沙門堂本堂
|
 |
|
阿武山
緑井からの眺望 |
 |
阿武山(586m)は、かつては観音信仰の山として崇められていた。 大蛇退治の伝説の残るこの山には石の祠や石碑も点在している。その端正な山容は市内中心からも眺められるが、太田川対岸からは巨大な象の形にも見えることから象山の呼び名もあるという。頂上付近からの展望は素晴らしく市内一円と瀬戸の島々が一望できる。
2014年夏に集中豪雨で土砂が麓の居住区に流れ込み多数の命が失われ周辺一体に甚大な被害を及ぼす大規模土砂災害が発生した。 |
|
阿武山
高陽からの眺望 |
 |