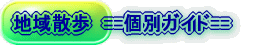
広島の狛犬とは形が大きく異なり珍しい
「地域情報」の掲載対象地域以外の情報ですが、前ページの情報と関わりがあるので参考までに珍しい[肥
前狛犬]を紹介します。
国内各地の神社前に鎮座する[狛犬]はもともと、その土地特有の形態をしていた様であるが、時代とともに
文化や物資の交流で他の物が持ち込まれ、複製や合成の体形のものが制作されている。それ故、今では研究
者の間でも、それらの分類に差異が見える。
しかし、「広島玉獅子」・「出雲構え獅子」 などは独自の形態がよく維持され、他のものと明確に見分けること
ができる。
当然、広島は前者、山陰地方は後者が広く分布している。
[広島玉獅子]広島型----- 大きな玉に前脚を乗せた体形。 素材は花崗岩のものが多い。
起源は1800年の初め頃から、広島の尾道あたりで造られ始めた。 (尾道型とも呼ばれる)
[出雲構え獅子]出雲型 ----- 頭を低くし、後ろ脚を立てて尻を高く上げ、飛びかかりそうな体形。
宍道湖畔を産地とする “来待石(きまちいし=砂岩)” を素材とし、柔らかい石質を生かし
て美麗な細工が施されているものが多い。 但し、砂岩製なので、風化には極めて弱い。
一方、ここで紹介するのは[肥前狛犬]。
[肥前狛犬] ----- 佐賀県と福岡県、長崎県、熊本県の一部に分布しており、16世紀後半から18
世紀後半(160 〜 170年間) に制作されたもので、30 センチメートル 前後の小型で実に素朴
な体形 をしている。
***** 九州を観光旅行中、偶然訪れた郷土資料館の展示会場で、「広島で見られるものとは全く形を異に
した“狛犬”」 を発見。 素朴な表情や体形で「これも 狛犬 なのかと」 驚いた。
珍しく興味深いものでしたので、それを”HPで紹介しては”と考え関係者に打診したところ、 写真撮影やHPへ
の掲載許可を頂いた。
以下の写真 と 先に紹介している 我がまち の 狛犬 とを対比し、いかに異なるかを実感してください*****
![我がまちの [狛犬] に戻る](button1.gif)
Copyright(C)2016,12 .Chiki-jjyouhou-hassinkai
![]()
![我がまちの [狛犬] に戻る](button1.gif)