| 江戸時代、物資を大量に運ぶ時には船が使われていました。広島城下の場合、太田川の7つの分流が流れていたため舟運が発達し、様々な物資が川船によって運び込まれました。 明治時代になっても状況は変わらず、川舟の数はピークに達しています。絵は現在の中区土橋町、本川の西岸にあった問屋さんの様子で、川舟で運ばれてきた米が荷揚げされています。この周辺は多くの物資が荷揚げされるにぎやかな場所でした。 なお、画面右手に描かれている灯籠は「常夜灯」と呼ばれるもので、夜間に本川を航行する船の目印になっていました。この常夜灯は現在同じ場所に復元されており、舟運が盛んだった時代を忍ぶことができます。 |
||||
|
||||
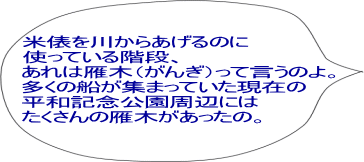 |
 |
|||
|
|
||||