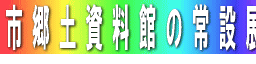
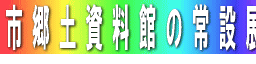
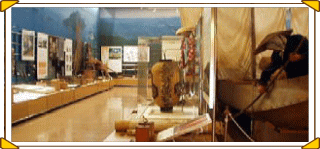
常設展示風景
| 郷土資料館の位置する宇品地区は豊かな干潟だった!郷土資料館の建物はもともと何だったのか?かつて日本一の生産量を誇った“かもじ”とは?広島を代表するカキ養殖など、豊かな自然と人々の努力に育まれた広島を知るために必見の資料をテーマ毎に1階で紹介しています。 入ってすぐのところにある地形模型では、人々の生活の舞台となった広島の姿を示し、伝統的地場産業の分布状況などを知ることができます。また、それぞれのコーナーには、学習の手引きや解説シートを用意しています。さらに詳しくは、テーマ毎に資料解説書や調査報告書がありますので、ご利用ください。販売もしています。 それでは、常設展示の主なものをご紹介しましょう。  |
| ご案内は以下の各タイトルをクリックしてください |
|||
| 県令「千田貞暁」と宇品港 | |
 |
現在、広島の海の玄関口となって多くの人々でにぎわう宇品地区は、明治の初め頃まで大型の船は、船着場へ直接入ることのできないほどの広大な遠浅の海でした。その干潟は、人々の生活の場でもありました。人々は盛んにカキやノリの養殖やアサリなどの採取を行っていました。明治13年(1880)、広島県令(県知事)となった千田貞暁は、広島をより発展させるためには、大型の船が入港できる港を建設する必要があると考え、沖に浮かぶ宇品島までを地続きにして港をつくる計画を立て、明治17年(1884)に築港工事を始めました。工事は、干潟を生活の場とする人々の反対をはじめ、数々の困難にぶつかる難工事でしたが、明治22年(1889)、約5年もの工期と当初の予定を大きく上回る莫大な費用をかけて完成しました。 |
| 宇品陸軍糧秣支廠から郷土資料館へ | |
| 明治27年(1894)の日清戦争以後、広島には陸軍の施設がたくさん造られました。明治30年(1897)、陸軍の糧秣の調達と補給を行う専門の常設機関として、宇品陸軍糧秣支廠の前身である陸軍中央糧秣廠宇品支廠が広島市宇品海岸に設置されました。また同年、広島陸軍兵器支廠が、明治38年(1925)には、陸軍被服廠広島派出所(のちの広島陸軍被服支廠)が設置され、広島に糧秣・兵器・被服の三支廠がそろいました。その後、宇品陸軍糧秣支廠は、明治44年(1911)に缶詰工場と新庁舎などを新たに宇品御幸通西側に建設し、移転しました。現在の郷土資料館の建物は、糧秣支廠の施設の一つである缶詰工場だったものです。この缶詰工場では、牛肉缶詰が生産され、特に大正12年(1923)の関東大震災で東京の陸軍糧秣本廠が被害を受けて以後は、牛肉缶詰製造はもっぱら宇品で行われました。 |  |
| 昭和20年(1945)8月6日、日本と戦争をしていたアメリカは、原子爆弾を広島に投下しました。缶詰工場は、爆心地から約3.2㎞の距離に位置していたため火災は起きませんでしたが、爆風で窓ガラスは割れ、北側の屋根の鉄骨は下向きに折れ曲がりました。戦後は、民間の食品会社が使っていましたが、昭和50年(1975)代の初めには使われなくなり、昭和60年(1985)、原爆の爆風の傷痕を保存して復元された建物は、郷土資料館として生まれ変わりました。建物は、広島市の重要有形文化財に指定されています。展示では、宇品陸軍糧秣支廠の缶詰工場の様子などを紹介しています。 | |
| カキ養殖 | |
 |
天然のカキを食べていた人たちがカキ養殖を広島湾でいつから始めたかは、よく分かりませんが、室町時代の終わり頃の天文年間(1532~1555)に安芸国で養殖法が発明されたといわれているという記録があります。江戸時代の初め頃から干潟に竹ヒビを立てる養殖法が行われるようになり、昭和の初めまでつづきましたが、昭和28年(1953)に孟宗竹で組み立てた筏で試験が行われて以後、筏式垂下法による養殖が急速に普及し、生産量も飛躍的に増えました。広島湾を中心に生産される広島県のカキ生産量(むき身)は、現在、日本全体の半分以上となっています。 カキの養殖が広島湾で古くから盛んになった背景には、太田川が運ぶ土砂などによって広大な干潟が沿岸部に作られたこと、太田川から流れ込む栄養分豊かな水に恵まれたことなどの絶好の自然条件がありました。 展示では、約2000万年前のカキ貝の化石、カキ養殖史、養殖法やカキ船によるカキの販売などを紹介しています。 |
| ノリ養殖 | |
|
かつて広島湾頭に広く形作られていた干潟は、波静かで、有機質を含む川の水と海水が混じり合い、ノリの生育に絶好の条件を備えていました。江戸時代初め頃、仁保島(現
南区)では自生したノリを生のまま食べたり、乾燥させて遠方へ送ったりしていたという記録がありますが、広島におけるノリ養殖の起源は、明らかではありません。しかし、ノリは、カキとともに古くから広島の特産として知られてきました。江戸時代中頃には、メダケやコザサを用いたノリ養殖が始められました。特に、江戸時代の終わり頃にノリを薄く精製した漉きノリが西国で初めて広島で作られるようになり、大きな発展を見せました。 |
 |
| 缶詰 | |
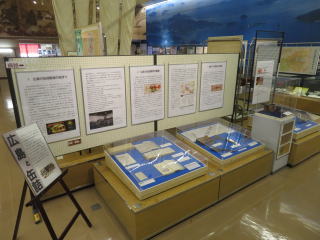 |
現在では廃れてしまいましたが、戦前の広島は全国屈指の缶詰生産県でした。 その背景には、広島では中国山地で牛、瀬戸内海の水産物、蔬菜や栗、松茸などの産物が豊富に安く入手できたことがありました。明治期以来、第五師団を擁し、陸軍の兵站を支えた宇品港や、呉に鎮守府、軍港を抱えていたこともあり、携行性や保存に優れ、調理もいらない缶詰、とりわけ牛肉の缶詰は需要が急増していき、広島では明治~昭和初期には全国の7~9割を生産していました。 昭和に入ると、牛肉のほかに果実缶詰、とりわけみかん缶詰の製造が急成長します。アルカリ剥皮法による技術を導入したことによりみかん缶詰の大量生産が実現し、海外への販路が開かれました。 原爆で壊滅的な被害を受けたものの、いくつかの業者が事業の再開を果たしました。 その後、昭和50年代からは減少を続け、今ではほとんど生産されていません。 |
| 米づくり | |
| 稲は日本人にとって、古くからもっとも大切な作物であり、広島市域でも盛んに米づくりが行われてきました。明治以降、産業の工業化が進んで都市が拡大してくるようになって、しだいに近郊農業として野菜を栽培する農家が増えてきました。特に、近年、その傾向が顕著になってきましたが、現在も稲は、安佐北区や安佐南区の農業地域などを中心に栽培され、その作付け面積は、他の農産物の合計を上回っています。しかし、生産額では、野菜が米を大きく上回って第1位となっています。 現在の広島市域では、都市的地域以外の農業地域が稲作主体の地域となっています。都市的地域では、高度な栽培技術を生かした集約的農業が営まれており、特に「広島菜」を始めとする広島市の野菜生産額の約80%が生産されています。 展示では、米づくりの1年の作業などを紹介しています。 |
 |
| あさづくり | |
 煮扱ぎ屋の庭先模型(再現) |
“あさ”は、古くから繊維植物として栽培され、衣服やロープ、漁網などの原料に利用されてきました。10世紀初めの『延喜式』には、安芸国からも“あさ”の加工品を貢納した記述があります。広島市域でも、中世以後盛んにつくられるようになりました。特に近世以降、太田川の舟運が開発されるにつれて栽培地域も広まり、現在の安佐南区古市などを中心に“あさ”の商品化が進み、一大生産地に発展していきました。古市における生産額は、大正8年(1919)にピークを迎えますが、その後、綿糸の漁網や化学繊維の普及に加え、経済不況や近代化の遅れなどによって、その生産は急速に減少し、昭和30年代にはあさづくりの歴史を閉じることになりました。 |
| かもじづくり | |
|
女性が自分の髪で日本髪を結うときに、髪型を整えるために使われた入れ髪、添え髪のことを“かもじ”といいます。広島市安芸区の矢野の“かもじ”づくりは、江戸時代初めの寛永年間(1624~1644)に大坂屋吉兵衛が始めたとされています。 |
 |
| 和傘づくり | |
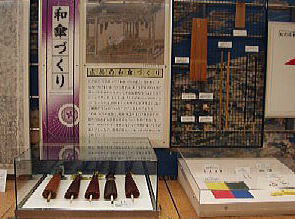 |
広島における和傘づくりの歴史は古く、元和5年(1619)浅野長晟が藩主として入国した際、和歌山から移住して藩の傘御用を務めた傘屋庄右衛門に始まるといわれています。安永9年(1780)、広島から他国へ移出した傘は、13万本に及ぶという資料もあり、和傘づくりがとても盛んであったことが分かります。また、幕末期における広島城下の傘職人は、ロクロ師や傘張骨師などを合わせて約130人を数え、藩も積極的に助成していました。 |
| 下駄づくり | |
|
広島県内では、全国に先駆けて機械による下駄づくりが始められた福山市の松永が有名ですが、かつては、多くの地域で下駄がつくられていました。広島市域では、安佐北区落合一帯が盛んでした。この地域の下駄づくりの歴史は、江戸時代初期にまで溯るといわれ、元和8年(1622)、諸木村(もろきむら)の吉備津屋清四郎が備中板倉(現在岡山市)で技術を習得して帰り、下駄をつくり始めたと伝えられています。その後、農閑期の余業として周辺の村々にも広まり、広島城下にも近く、太田川上流地域から安定して木材が供給されるなどの好条件を背景に盛んにつくられるようになりました。明治中期以降、県東部の松永で雑木を使った下駄の生産が増加すると、これと競合しない桐下駄
(きりげた) の生産に転換していき、明治末期から大正にかけて生産のピークを迎えましたが、昭和になると急速に衰退し、落合では昭和30年(1955)代後半、安佐南区の八木では昭和60年(1985)代になくなりました。 |
 |
| 山まゆ織り | |
 |
広島市安佐北区の可部町や安佐町でかつて行われていた山まゆ織りが、いつ始まったのかよく分かりません。元文4年(1739)の記録に安佐町の鈴張、小河内での山まゆ織りの様子が紹介されています。 |
| 舟 運 | |
|
中国山地に源を発し、多くの支流と合流する太田川は、その周辺の人々の生活と深い関わりを持ってきました。特に、河口のデルタ(三角州)に毛利輝元が広島城を築いてからは、太田川の舟運は、広島城下と内陸部を結ぶ物資輸送の大動脈として大きな役割を果たしてきました。太田川本流では薪・炭などの林産物が、太田川の主要支流である三篠川では年貢米が主な荷物でした。明治時代に入り、藩の統制がなくなり、自由に経営できるようになった舟運は、ますます盛んになりましたが、大正時代以後、陸上交通の発達につれて衰え、ダム建設による水量の減少もあって、昭和時代に入って消えていきました。 |
 |
| 昔の暮らし | |
 |
みなさんのおじいさんやおばあさんが子どもだった昭和30年代に家庭に入ってきた道具により、大きな生活の変化が起こりました。スイッチひとつで照明・暖房・炊事ができる道具やテレビの普及です。現在のみなさんの生活スタイルにつながる変化でした。 展示では、昭和30年代前後で生活スタイルがどのように変化したかをさまざまな道具を通して紹介しています。 |