![]()
| 江戸時代になると、菜種油やろうそくが盛んに作られるようになり、それらを使ったさまざまな照明具が広まっていきました。 代表的な灯りの道具として、室内では行灯や燭台、屋外では提灯や龕灯が使われました。 行灯おもに室内で使われていた照明具で、油皿やロウソクの火が風で消えないように、木枠に和紙を貼っています。もともとは屋外を歩くとき、足元を照らすために用いられていました。室町時代ごろから使われていましたが、持ち歩きに便利な提灯や手燭が広まると室内に置く灯りとして使われ、さまざまな形のものが作られました。 |
||||
|
||||
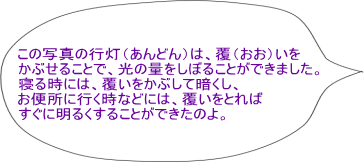 |
 |
|||
|
|
||||