| 件名 | 12 八幡神社 |
|---|---|
| 所在地 | 佐伯区八幡三丁目 |
| 写真 |  |
| 内容 | 明治41年(1908)に明治政府の一村一社の趣旨に沿って、旧八幡村では村内神社の合併を進めた。大正4年(1915)8月7日に、稲生神社(寺地村)宝神社(寺田村)、新宮神社・古保理神社(利松村)、大歳神社(口和田村)、稲荷神社(高井村)、大歳神社(口和田村)、稲荷神社(高井村)、大歳神社・竈神社(保井田村)の8社を合祀して、旧寺地村内の稲生神社の鎮座地に集め「大正神社」と称した。 昭和3年(1928)に、旧中須賀村梅王田(バイオウダ)の「八幡神社」と大正神社を合併し現在の「八幡神社」となった。因みに中須賀村の八幡神社には、神功皇后が瀬戸内海を航行の途次に立ち寄ったという言い伝えが残っている。八幡地区では最古の神社となっており、「やはた」の地名の起源となり、それに続く南には今も木船と言う地名も残っている。絵師岡岷山が『都志見往来日記』に載せた、八幡川沿いの八幡神社はこの神社と思われる。 祭神は八幡神を主神に相殿神を併せ、合祀された全ての祭神を祀っており、毎年の秋季大祭は八幡地区の風物詩となっている。境内のイチョウの大木も、紅葉の際には黄金色となり神域を形成している。 |
| 地図 | 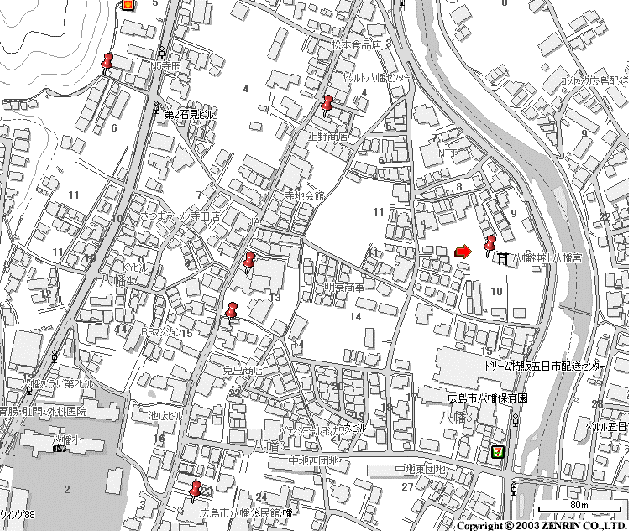 |