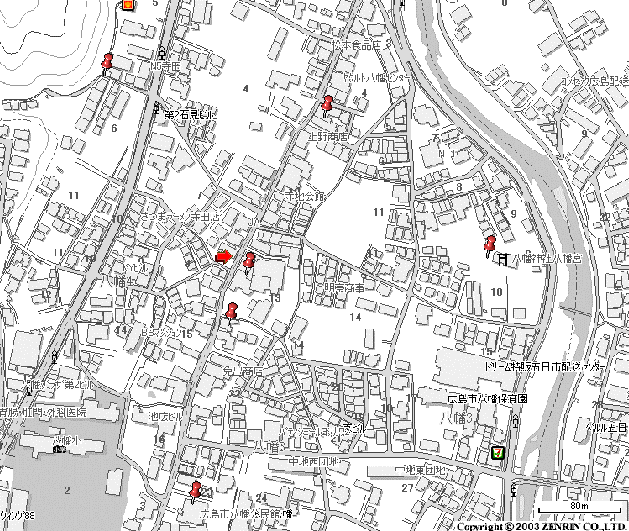| 内容 |
八幡地区を南北1キロメートルほど貫く、旧県道沿いの八幡本通商店街を北へ進むと、白壁の建物に煉瓦造りの煙突が残る。明治40年(1940)創業の「八幡川酒造」は、酒蔵の中に入るとひんやりとし、貯蔵タンクからはほんのりと酒の香りが漂う。酒造りの水は、今も地下18メートルを流れる八幡川の伏流水を汲み上げているという。 日本の酒造りは江戸末期に、灘などの大阪湾沿岸に始まったとされる。広島は吟醸酒の生みの親とされる、安芸津町三津出身の杜氏三浦仙三郎でも名高いが、明治40年頃には、安芸津や西条で酒造りが始まった。その頃既に八幡村でも中地の池田や保井田の児玉の両醸造所で酒造りが始まった。大正13年(1924)にこの2つの酒蔵が合併し「八幡酒造」となり、操業を続け昭和26年(1951)年に現在の社名となった。「八幡鶴」や「八幡川」などの大吟醸酒は、全国新酒監評会で3年連続の金賞受賞でその名が全国にとどろいた。また8ミリビデオ撮影の腕前や、新藤兼人監督との親交で知られた川本昭人前社長は有名である。平成元年(1989)から「街づくり」の一環として、新酒のできる毎年3月に「八幡川蔵開き」が開催される。当日には酒蔵見学のほか、利き酒やおでん・焼鳥などの屋台もあり、餅つき大会なども含め、毎年数百名の愛好家や一般客で賑わっている。 |