| 件名 | 15 公聚館跡 |
|---|---|
| 所在地 | 佐伯区八幡3丁目22−33 |
| 写真 |   |
| 内容 | テレビも自動車も普及していない明治・大正期に、農村での重要な娯楽の一つとして、地元の芸人や旅芸人による芝居興業があった。これらの興業は村々の広場に、板囲いやムシロを下げて作った小屋掛けの会場で行われたものである。八幡村でも明治45(1912)年頃には、大字中地字石亀の現在の渡辺ビル敷地に、「公聚館」が建設され、従来の芝居興業などが行われた。公聚館はその後村人の娯楽の殿堂として、言わば現在のカラオケに近いものとして、昭和15・6年頃まで存在した。公聚館跡の前を南北に走る、道幅5メートルほどの狭い旧県道に沿う、本通商店街の片側には、江戸時代に造られた川幅1.5メートルの農水用路がある。現在一部は蓋で覆われてはいるが、八幡川から引き込んだ水を、今も満々と湛えて流れている。昔の八幡川は氾濫が多く、五日市の人々が水害で困り果てたため、江戸初期に竹之内〜皆賀間に新しく川筋を付け替えた。このため五日市の水田は水不足となり、慶安4年(1651)に寺田に井堰を設け灌漑用の水路を開作した。その後八幡川の水を五日市水田地帯に流し、「五日市用水路」として利用されたものである。 |
| 地図 | 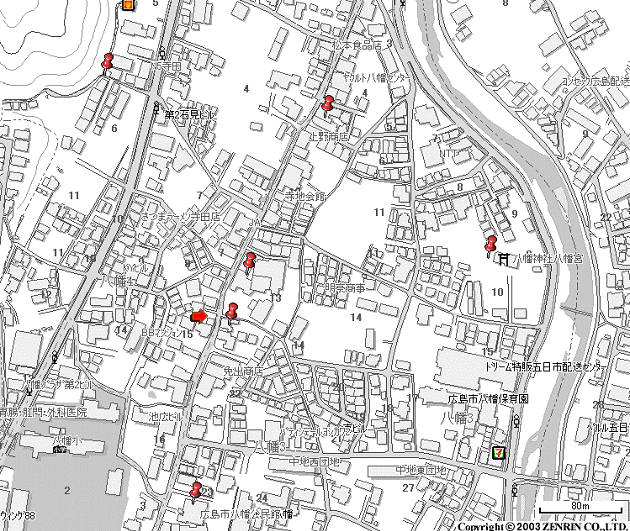 |