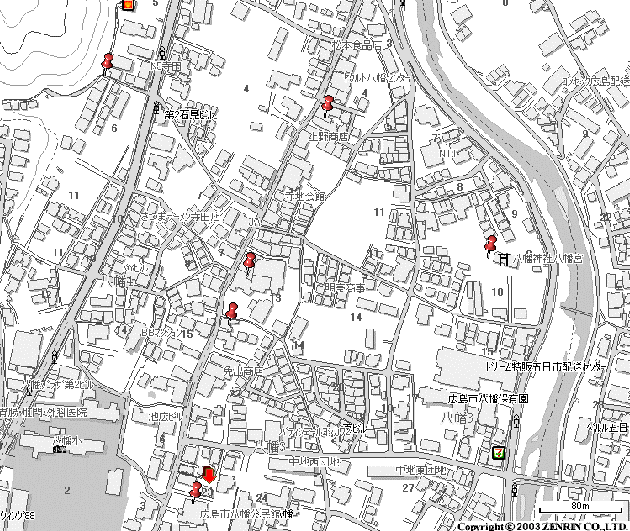| 内容 |
江戸時代に八幡地区には、利松・口和田・高井・寺田・中須賀・寺地・保井田の各村があり、八幡川と支流の石内川や保井田川に恵まれ、山間に沃野が広がっていた。古代には佐伯郡の主邑の「佐伯郡家」が置かれ、古代山陽道=影面の道に沿い「大町駅家」も所在していた。古代の条里制の遺構も確認される。現在の「郡橋」や「古保利神社」の跡地はその名残で、中世には周辺部山稜に幾つもの山城が置かれ交通の要衝となっていた。 近世には廿日市宿と出雲石見街道に沿う古市に至り、「沼田郡往来」が古代山陽道に沿い設置され、八幡地区のJA付近にその一里塚が置かれていた。八幡川の舟運も郡橋まで遡行しており、物資の集散地として発達していた。明治22年(1889)に旧村は併合され、新しく「八幡村」が誕生した。中須賀村と寺地村は明治12年(1879)に、いち早く合併し中地村となり、明治中期以来大字として旧6村は継承された。明治期の合併により「八幡村役場」が開設され、これが現在の八幡公民館の敷地として受け継がれた。大正15年(1926)に当時の皇太子=昭和天皇が広島に行幸され、その際立ち寄り松の苗を植えたと言われている。しかしこの時の松は枯れてしまい、現在の桜は昭和22〜3年(1947〜48)頃に、桜の苗の配布がありその時に植えたものである。因みに当時皇太子が八幡村に来られたことは、記した文献類は現存していないので分からない。 |