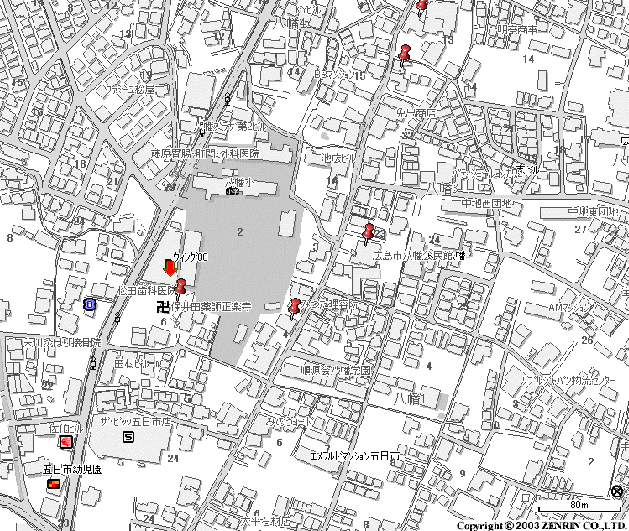| 内容 |
八幡小学校の南隣に、「お薬師さん」の名で知られる「保井田薬師堂」がある。古来、縁結びや眼病にご利益があるとされ、地域の人々の信仰を集めている。薬師堂の世話をされている谷口喬さんの話では、毎年2月11日の縁日には、沿道に見世物小屋や屋台が立ち並んで賑わい、戦前は参拝客が3キロメートル先の楽々園まで続いたという。本尊の薬師如来坐像は、天平3年(731)の行基の作と言われる。行基は大仏造営の大勧進の勅語を受け全国を巡回し、厳島に向かう沖の船から極楽寺山の方角に瑞光を放つ大杉を見て極楽寺山に登り、この霊木から先ず千手観音(極楽寺山の本尊)を彫刻し、次に薬師仏(保井田の薬師)の像ほか48体の阿弥陀仏を作ったと伝えられる。行基により創建されたお堂は、当初は現在の薬師が丘1丁目1番地の、通称「岩石單山」(いわぐろやま)に安置された。その後の大同2年(807)に巡錫中の弘法大師は、この地に立寄り開眼供養を営み、正式に「岩石單山正楽寺」を開き、それ以来真言密教の道場と定めた。やがてこの正楽寺は「保井田の薬師さん」と呼ばれ人々の信仰を集めた。 明治12年(1879)に保井田の地から現在地に移設されたが、旧地の裏山を開き造成された「薬師が丘団地」は、これに因んで名付けられた昭和末期の地域名称である。「里人の語るをきけば浄るりの 仏も古き時代物なり」と、栗本軒貞国氏の名歌はある正楽寺の紹介記事に掲載されている。 |