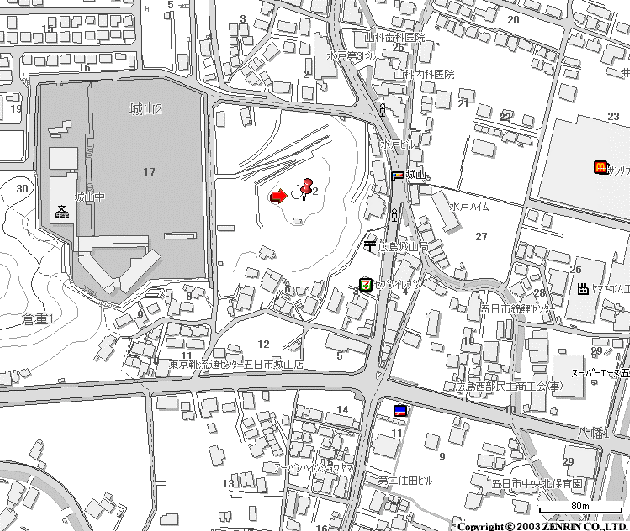| 内容 |
薬師が丘団地の南側に保井田と地毛との境に、城山と呼ぶ小山があり中世の池田城跡が残っている。この地は畿内と九州を結ぶ古代山陽道が通り、古くから交通の要衡であった。平野部は厳島神社の神領地でもあったため、軍事上の拠点としても重要な場所であった。 池田城は摂津国池田城主・池田教依の子で、南朝の楠木正成孫とも言う池田教生の城と言われている。摂津池田家は後の備前藩主池田家や因幡鳥取藩主池田家一門の祖にあたり、二代目城主たる池田教生がなぜ五日市に城を築いたのかは不明である。南北朝時代に同じ南朝方で働いた僧祐覚の出た五葉院が、池田城の山麓にあることも大きく関係する。池田城の西には池田屋敷の田地名を残し、五葉院の南側の谷蔵谷に近年まで古い五輪の塔があり、五葉院をたよった楠木正親夫人の墓とも伝えられる。摂津池田家の築城時代は14世紀中期から中期後半と、戦国時代になって弾為虜なる武将が城主になったと伝える。厳島神社の領地争いは、武田・尼子・大内の三勢力の間で行われ、池田城もかなり形状も変化があったと推測される。毛利元就は弘治元年(1555)に陶晴賢を破りその行賞として高木信安を城主とした。毛利輝元に替わり福島正則が広島城に入り、池田城主信安の子信行の代になると、毛利の旧臣で地侍的性格を残したものに対しては帰農を勧めた。しかし反対した信行を元和元年(1615)に急襲し滅ぼし、それ以後この城は廃城となった。因みに五葉院は城山の北のごえん谷(五葉院谷)と呼ばれる地にあり、後に五日市に移り光禅寺となった。 |