| 件名 | 22 胡粉工場跡 |
|---|---|
| 所在地 | 佐伯区八幡東二丁目 |
| 製造方法 | 胡 粉 の 製 造 方 法 や 用 途1. 牡蠣殻を水で洗い、水車の石臼でつき砕く。2. 砕いた殻を'小米どおし'でおろし、水を入れながら豆腐を挽くように臼で挽き、桶に入れる。3. 桶(1番桶)に溜まったら、掻き混ぜて水で流し次の桶(2番桶)へ送る。4. 同じように3番・4番・5番・6番桶まで送る。5. これを大きな塗り壷にいれ、半日余り置くと上部が清水のように澄み、下の方に胡粉が沈殿する。6. 塗り壷の中へ多くの孔があいた樋をとおし、この樋の孔から澄んだ水を吐き出さすと、胡粉だけが残る。7. この胡粉を平らな箱に汲み取って干す。8. これが乾くと1.5〜1.8センチ厚の板状の胡粉となる。注:この様に文化11年(1814年)頃から中須賀村(今の中地)で製造された胡粉は、ふすまの下塗り塗料や芸者の(首に塗る)化粧品として重宝がられ、大阪方面にまで出荷された。 |
| 内容 | 『五日市町誌』によると、文化11年(1814)旧中須賀村の農業従事者で祖平次という者が胡粉製造法を修得し、広島藩府へ願い出て許可を受け、水車を設備し胡粉の製造を始めたとの記述がある。佐伯郡内では他にはなく、工程は牡蠣殻製を洗って水車の石臼で搗き砕き篩いにかけておろす。さらに桶に入れて水を流し入れ、その工程を6回くらい繰り返し乾燥し板状の胡粉とした。なお乾かないうちに「水胡粉」として四斗樽に詰めて、大阪方面に送っていたという。 この胡粉は化粧品として利用され、女性の白粉の原料として、また白色顔料として最高の品質と好評された。同工場ではその後も操業はしていたが、昭和15年(1940)頃に閉鎖し現在ではその様子は全く伺えない。 |
| 地図 | 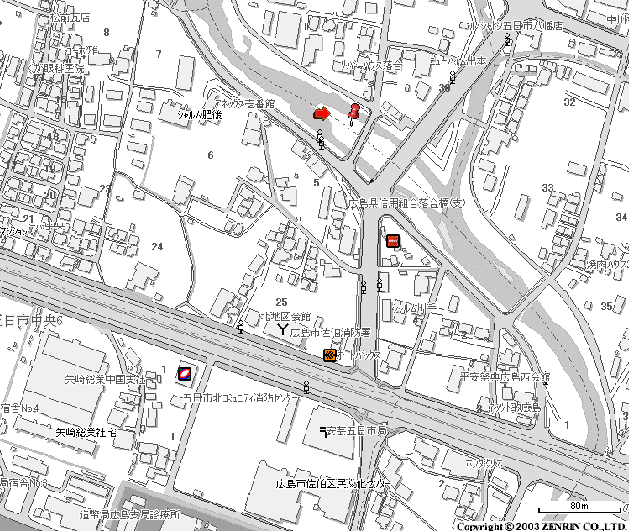 |