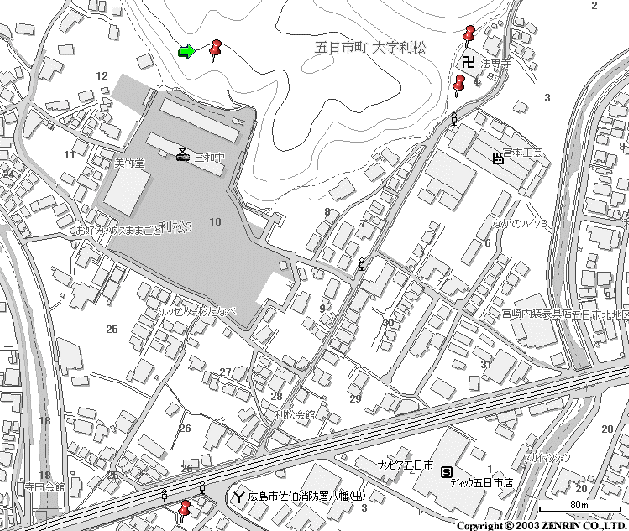| 内容 |
八幡地区北辺の山城の一つであり、平安末期源平合戦の頃に「利松孫右衛門」の居館があったという。利松には古代山陽道の「大町駅」が設けられ、「古代佐伯郡家」も置かれていた。今の郡橋付近と思われ、近世の八幡川舟運の終点でもある。付近には商店や倉庫が建ち並び、石内・河内・湯来方面への分岐点となり、郡橋西詰下に今も道標が残っている。「宮尾城」を中心に多くの支城があったと思われ、直下の山頂付近は平らに整地され曲輪の遺構があったと思われ、尾根伝いには人の往来や防衛のための砦や通路が取巻いている。 中世の山城の多くがそうであるように、普段は麓に居住しいざ合戦の折には山城へ篭るものと思われる。戦国末期から大坂城や江戸城を始め、毛利氏の広島城など交通の便利が良い川筋や、海への出口の三角州に築城される例が多い。中世の城は防衛を第一に考えられたようで、家族は麓の居館に残し戦闘員が山に篭るスタイルが定着した。源頼朝の弟の範頼に仕えた家臣利松孫右衛門のものと伝える小祠は、三和中学校裏山の宮尾城の麓にあり「熊野新宮宮御前」と呼ばれていた。後に利松氏は絶えたが松の大木が残り、文明年間に村民が再建し新宮神社と呼ばれる氏神となった。その後宮ノ前や宮尾城共に神域となったが、福島正則の治世時代に社領は没収された。 |