| 件名 | 06 廻国塔 |
|---|---|
| 所在地 | 佐伯区利松三丁目 |
| 写真 |  |
| 内容 | 利松の法専寺西側の古代山陽道と推測される山道沿いに、記念塔と地蔵尊が立っている。この記念塔には次のように刻まれている。 「奉納 日本廻国 寛永三庚午年(1750)・佐伯郡利松村」 「奉納 日本廻国 宝暦七年(1757)丑八月五日」 いずれも約250年前の江戸時代中期に、利松村の智真という僧侶が「実誉浄土大徳」をめざし日本全国を廻国巡礼し無事に帰ってきたことから、その記念にこの石塔を建てたものと言われている。全国を巡礼してこの祈念塔を奉納することで、僧侶としての地位と名誉を高めることを期待したのであろう。自らの健脚だけを頼りに全国行脚した体力と気力に脱帽するが、江戸時代の人々の徒歩での移動距離は、一日平均で十里(40km)と言われ、飛脚に至っては一日の移動距離が100kmを越えたと言う。江戸時代中期になると、街道の要所には茶屋等の休憩所が見られる。同時代に活躍した広島藩の絵師岡岷山が「都志見往来諸勝図」の中で八幡地区の風景を描いているが、河内峠に向かう街道沿いに茶屋が三軒描かれている。人々は一服して旅の疲れを癒しながら、一歩一歩旅の歩みを進めていった。 |
| 地図 | 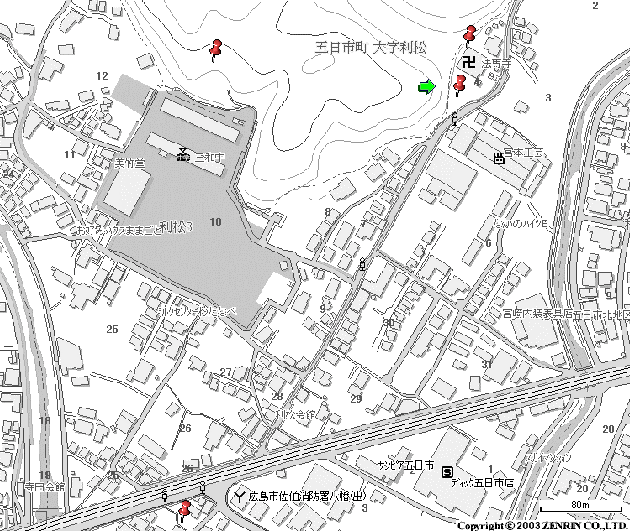 |