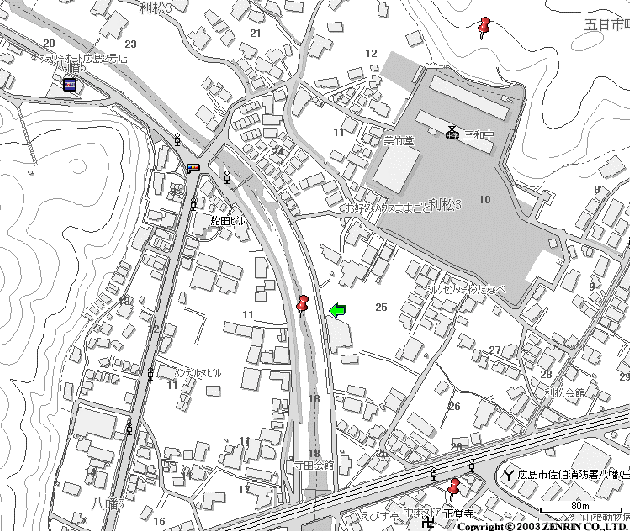| 内容 |
五日市平野の中央部は沃野となり、忘れ川として知られる三筋川と八幡川が流れている。八幡川は周辺山地からの土砂の流出が多く、一部は天井川となり氾濫を繰り返していた。17世紀半ばの江戸初期に、現在の五日市八幡神社と皆賀地区の小山の間を削り、八幡川の付替え工事が行われ、落合橋付近から山沿いに皆賀の方へ流れることとなった。五日市方面への水漏れを防ぐ強固な堤防が造られ、五日市方面への用水が不足することとなった。 五日市村は上流の寺田村に井手を設置し、寺田・口和田・中須賀・寺地・利松・保井田の6ヶ村から土地を借りて溝を掘り上げた。さらに五日市村の長林地に樋門を設け、平野に向け用水路を敷設し灌漑用水にあてた。この用水は八幡地区6ヶ村を通るので、借地料として昭和30年(1955)の五日市町合併まで、毎年2石2斗2升が支払われていた。そのために用水路からの利水や取水は許されず、五日市地区の田植えが済むまでには水に関する争論や訴訟が起こったという。 寺田井手は取水口から162間(291m)が、八幡川沿いにつけられ井手と称せられた。江戸時代には井出の補修が行われ、特に長い箇所は広島藩があたったという。井出近くの橋の名は「出口橋」と名付けられ、現在の「三和橋」の始まりとなっている。水害によりよく流れるつり橋で、昭和27年(1952)のルース台風では橋脚共に流された。また長林地の樋門の上は「笛免」と呼ばれ、保井田川と合流して水量が調整された。 |