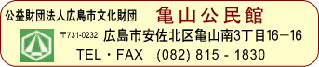![]()
第5節 地域住民の救援活動
| 1. 地域内の救援活動 | 2. 地域外の救援活動 |
| 1.地域内の救援活動 | |
| 安佐部隊の活動 8月6日、広島市上空に原子爆弾が投下された。 わずか数分後、可部上空を敵の大型飛行機が通過し、間もなく3つの大きな落下傘が、風にゆられ、「キラ、キラ」と、光りながら次第に落下し始めた。 落下傘は、その下に長い物体をつるしていた。 時刻は、午前9時15分ごろであった。 消防団員に、急きょ出動命令が下された。 サイレンは、激しく鳴りわたり、「時限爆弾だから、200m以上離れた所に逃げるように・・・・」との警報が発令された。 地域住民は、それぞれクモの子を散らすように、一目散に家族づれで松林、竹やぶへと避難した。 その夜は、竹やぶの中で一睡もせず、不安の一夜を明かした。 しかし、何も起こる気配はなかった。 3個の落下傘は、亀山村大毛寺、福王寺山ろくの若藤丈吉宅から、300mに離れた山林中に1個、同じく福王寺山ろくで、先の地点から600m離れた上大毛寺山中に1個、今一つは、大毛寺、報恩寺裏から50m離れた両延神社の森の下の田の中に、それぞれ落下した。 安佐郡三入・大林・亀山・久地・日浦の各町村、約100名の防衛隊、安佐部隊(隊長 熊谷予備准尉)も非常召集された。 亀山村今井田の隊員神田実氏(当時19歳)は、アゼの草刈りをしていて、閃光を感受したという。 亀山村役場吏員は、自転車を飛ばし連絡、直ちに出動し、大毛寺に落下した落下傘についていた円筒の警備に当たった。 円筒の周囲に、アゼを作って水を引き、遠まわりから警戒していた。もちろん、地域住民は通行止めとなり、その周辺を行き来することも見に来ることなども、絶対に許されなかった。 安佐部隊は、河戸、梶山氏宅前と亀山農業会の前で、「通行禁止」の立哨に当たった。 2、3日後、兵隊が到着し、その命令で馬車に乗せ、可部地方事務所へ運び、しばらくは廊下に置いていたが、第2総司令部が持ち帰った。 落下傘についていたひもは、現在、可部の願船坊と広島平和記念資料館に保管されている。住民の中にも、いくらか拾って記念に所持している者もある。 医師を中心とした救護団の活動 8月7日、可部署管内祗園・可部地区2班の救護活動が始まった。7日朝、可部警察署2階に、医師・薬剤師が参集し、可部地区救護団を編成した。団長に外科医笹木武誰氏が指名された。 それぞれの救護団の医師は、午前中は自宅で無料奉仕の診断、治療を行い、午後は、学校・寺院などの病院に出張しての診療を続けた。患者の中には、頬部切創を縫合して、発音・摂食を可能にすることができた者もあった。 おもな症状としては、倦怠・嘔気・食欲減退・血性下痢・皮下溢血・脱毛などが、定型的な症状であった。 笹木医師の話では、一朝に50枚もの死亡診断書を書いたことがあるという。改めて原爆の被害のものすごさを思い知らされ、身の毛のよだつ思いである。 婦人会・町内会などの活動 8月6日、午前9時過ぎのことであった。 顔も手も足も真っ黒、衣服も焦げてボロボロ、頭髪もクシャクシャ、まるで裸同然・・・・、そのうえ、顔や手の甲は火ぶくれし、血を流しながら、素足のままで、逃げ惑う被災者が可部街道に殺到し始めた。 避難者は、みんなぼう然自失のありさま、これこそ、この世の生き地獄、さながらであった。 可部町民は、沿道に清水とコップを手に、「水をどうぞ、どうぞ」と接侍に努めた。口にする気力も余裕も持ちあわせていなく通り技けて行くものもあった。 初めのうちは、一見、軽傷で、自力で逃げ出すことができる人のようであった。午後2時ごろからは、重傷の兵隊や市民が、トラックや荷馬車に乗せられ運ばれて来始めた。 負傷者の輸送は、9日の昼過ぎごろまで続いた。 病室とは、名ばかりで、床に敷くゴサさえ十分ではなく、かろうじて毛布1枚に、からだを横たえているありさまであった。 「蚊取り線香」もなく、扇風機もなかった。 窓は、あけっぱなしで、網戸の設備もなかった。 連日、30度を越す、汗ダラダラの部屋の中は、熱気むんむん、悪臭が鼻をついた。 それもそのはず、負傷者の皮膚は、垂れ下がっているもの、ただれて膨れあがって、ウミが流れ出ているものが大半だった。それに、はえが止まって、ウジが発生するという、見るに忍びない痛々しさであった。 「水をくれ」と呼ぶもの、「痛い、痛い」と、のたうちまわろもの、「殺してくれ、死んだ方がましだ」と、うめくもの・・・・、看護人は手の施しようもなく、ただオロオロするばかりだったという。 そのうえ、医薬品は少なく、看病は困難をきわめた。蒸留水で傷口を洗ったり、食塩水を作って、消毒や洗浄に使ったりした。 薬剤がなかったため、じゃが芋をすりつぶして、のリ状にして火傷面に塗ったり、きゅうりをすって、その汁を傷口に塗ったり、つわぶきの葉を、はったりという治療しかできなかった。 傷口に赤チンを塗ったりしたが、それでもウジが発生し、はい出してくる。看護人は、それを、ハシで1匹1匹取ったのである。 死者も続出した。原爆投下後、7日から8日が最も多かった。8月26日まで続いた。 死体の焼却は、地域の男子にゆだねられた。 軍の命令で、「午前10時に点火。午後5時、消スベシ」とあったが、日の長い夏のこと、確実には実行されなかった。 余りの死者のため、各地区とも火葬場では間に合わず、山林の空地、河原などを臨時の火葬場にせざるを得なかった。 亀山国民学校で、3か月間の長期にわたって奉仕していた田中オカさん、泉キヨ子さん(現住は死亡)は、当時のことを次のように話していた。 病院に早変わりした当時は、病人の食べる野菜が一つもなく、毎日のようにカゴを背負って、大根・きゅうり・ナス・なっぱなど、各農家を一軒一軒かけ回って供出してもらった。 各家とも、野菜は、あまり作っておらず、収集には大変苦労した。 野菜集めが済むと、炊事の手伝い、重傷者の世話など、毎日のようにした。 おかゆをスプーンで、口の中に入れてあげた。 夜通し、うちわであおいであげたこともあった。 「ありがとう、ありがとう」「決して、ご恩は忘れません」と、手を合わせて、息を引き取っていった人のことなど、今でも脳裏から離れない。 ほんとうに、むごいことをしたものであった。 什事で一番困ったことは、毛布の洗濯であった。 洗濯場がないため、大きな厚い毛布を川まで運んだ。 石けんはなく、ゴツゴツの毛布を、手でもみ、足で踏み込むなどして洗った。 なにさま、血・うみがこがりつき、悪臭が鼻をつく毛布だけに、その苦労は並大抵のことではなかった。 干し場がないので、何枚も川原に広げて干した。 各地区の国防婦人会は、病院の炊事、看護のほかにも、いろいろと活動した。 被災者、避難者のために、各家庭を回り、住居の心配もした。 このころ、ほとんどの家庭に、家を失い、焼け出された人が泊っていた。 被災者のために、ふとん、衣類などの供出を各家に依頼し、困っている人に配分した。 物資の配給も中心になって行った。 戦後は、米をはじめ調味料、衣類など、すべて配給制度であった。 男手がないため、村役場、農業会などに、配給物資を取りに行き、それぞれの常会に持ち帰って配給をした。 戦死者の遺族、被災者あてに、それぞれ慰問の手紙を書いて、見舞激励を行った。 被爆負傷者、救援のための炊き出し、搬出 当時の大林村役揚の記録によれば、 「昭和二十年八月六日午前八時、B29広島上空ニテ投弾ス。 就テハ同日午后三時二十分、安佐地方事務所ヨリ、 大林村二国民義勇隊員。百名出動命令アリ、午后四時、可部警察署ヨリ握飯三千個ヲ七時迄二作レノ命令アリ、直ニ前記計画ニ依リ手配ヲナス。 第二回、炊出シ命令ハ、八月八日午后四時下命サル(三千個 但シ米ハ配給済 塩・薪ハ末配給) 第三回 炊出シ命令ハ、八月九日午前九時作製、搬出ヲ下命サル(其ノ他ハ同ジ) 第四回 八月十日 前回同様命令ヲ受ケ処置ヲアス(午前十時)」 となっている。 これは、三入・可部・亀山においても、量こそ違え、同様の命令が下されていた。 当時、米は供出制度が実施され、農家には、保有米以外の余裕は全くなかった。 握り飯用の米は、食糧営団の緊急配備で、農業会(現在の農業協同組合)から、各地区に米を持ち帰らせ、むすびとして作られ、広島市へ午後5時以降に持参された。 その握り飯は、各町村の国防婦人会会員の手によって作られた。 また、その搬出は、8月7日から8月10日まで、狩小川村-福木村-東練兵場経由で市内(八丁堀・紙屋町・皆実町)に入り、山佐運送のトラックで行われた。 帰路は、千田町―紙屋町-牛田町-十日市町-横川―祗園町経由で、被災者の輸送にあたった。 なお、8月11日から8月15日まで、広島市山口町、農興銀行跡に救護本部が設置され、その指令により市内の被爆者の輸送にあたった。 |
|
| 2.地域外の救援活動 | |
| 教職員救援隊の活動 8月6日、可部地方事務所から、安佐郡下の各学校に、救援隊として出動するよう、下記のような指令があった。 集会日時 8月7日 午前6時30分 集会場所 古市橋駅前 持参する物 学校にある救急薬品 隊長は、野平省三氏(当時 八木国民学校教頭)、副隊長は、村上昇氏(当時 落合国民学校教頭)、指揮は、山中義夫氏(当時 可部地方事務所主事)で、隊員は、郡内教職員35名余であった。 交通機関は、すべて麻ひ状態、そのうえ敵機が上空飛来とあって、隊員は、目立たないように、県道を避け、裏道沿いに、市内横川付近へと歩き続けた。 市内に近づくにつれて、被害、惨状のじん大さに、ただ、驚嘆のほかはなかった。 見渡す限り火の海だった。炎炎と燃えさかり、もうもうと立ちこめる煙をかいくぐりながら進んだ。 衣服は焼けちぎれ、傷だらけで、真っ黒な顔、裸同然の避難者が行列をなしていた。 横川踏切付近の沿道には、仰向けになったり、うつぶせになったり、重なり合ったりして、黒こげになって死んでいる人、人、人の山であった。これぞこの世の生地獄であった。 救援隊も何から手をつけてよいのか、皆目わからない始末だった。ともあれ、歩いて逃げられる人は後にして、命からがら、はうようにして脱出してくる負傷者を優先せざるを得なかった。 まず、安全と思われる新庄の竹やぶまで、担架に乗せて避難させることにした。 しばらくして、上空に敵機B29が飛来し、旋回し始めた。 隊員は、退却命令により、やむなく新庄の竹やぶに避難し、待機していた。 竹やぶの中は、焼けただれた人、重傷を負い血まみれになっている人・・・・でいっぱいだった。 「水をくれ」と、叫び続ける人も数知れなかった。 当時、隊員だった人の話では、「あの悲痛な叫び声」が、今でも聞えてくるような気がする。なかなか、耳の奥から消え去らないという。結局、この日は、敵機旋回のため救援は打ち切りとなった。 あくる日、8日は、八丁堀方面の救援に出動した。 火もようやく下火とはなったが、あたり一面、熱気むんむん、灰の海と化していた。 建物・家屋・樹木など、一切焼失し無惨な光景だった。 原子爆弾の強烈さ、恐ろしさをまざまざと見せつけられた。 残るは、かろうじて鉄筋の建物のみだった。屋根の丸い屋根が崩れ落ち、鉄骨のみを残した陳列館、八丁堀の農興銀行くらいのようだった。相生橋付近では、兵隊が馬の手綱を握ったまま死んでいた。馬の腹は、破裂し内臓が露出していた。 寺町表・裏の太田川では、火を逃れて川の中に飛び込んで死んだ人、川ばたの石段に、しがみつき、もたれかかって死んだ人・・・・の数は、数え切れないぼどだった。 師団司令部では、50人余の兵隊が整列したまま仰向けになって死んでいた。 医療救護班の活動 医療救護班として、7日から14日まで、大林村45人、延べ120人、三入村160人、延べ240人、可部町200人、延べ365人、亀山村175人、延べ280人が出動した。 これらは、三入村の医師1人を除いて、すべて一般町民で市内での医療活動を補佐した人々である。 また、警防団も出動した。 大林村は、12日から14日まで連日15人、延べ45人が牛田方面、三入村は、11日から13日まで連日30人、延べ80人が三篠・中島・十日市・紙屋町一帯、亀山村は、8日から13日まで50人、延べ120人が、三篠・中島・福島・白島各町一帯、可部町は、8日から12日まで75人、延べ185人が、三篠・十日市・中島・紙屋町・福島町各町一帯で、それぞれ救護活動に当たった。 これら警防団員は、すべて徒歩で出動した。延べ人員が、実人員と出動日数の倍数になっていないのは、日によって出動者数が違ったからであろう。 さらに、安佐部隊も10日昼ごろ救援に出動した。 白島の常盤橋たもとの交番跡に本部を置き、負傷者約50人を天幕に収容して看護するとともに、死者101人を近くの時計店跡で焼き、遺骨を瓦の上に置いて、縁故が少しでもわかるようにしておいた。 隊員は、皆、野宿で1週間任務についた。 安佐救護部長、戸田幸一氏(歯科医師)は、広島の北16kmの可部から、安佐郡祗園町の臨時救護所に応援にかけつけた。 戸田医師が持っていた治療用材は、ビタカンファー10本余、マーキュロとヨーチン少量、脱脂綿50グラム、ガーゼ10m、それに、ピンセットとはさみで、火傷用の油剤さえなかった。 救護所の棚に、なんのためか食塩を入れた大きな鉢があった。 戸田医師は、火傷を負った患者に、生理食塩水で湿布してみることを思いついた。 バケツに食塩と水を入れ、食塩水を作った。 近所の人に古衣を供出してもらい、これを引きちぎって、ガーゼや包帯のかわりにした。 治療をすすめていくうちに、救護所を頼って来る人が、みるみる増えている。皆、いちように皮膚が、黒か茶色に変わっている。 全身やけどで、声の出ないものもいる。 うめきと悲鳴。ときどき、待ちきれない重傷者が「ドタリ」と廊下に倒れる。 戸田幸一氏は、この重傷者たちと手持ちの薬と材料と思いくらべて、ほとんど、絶望的な気持ちになった。 「いったい、どうしたらいいのか」治療を開始する前に、廊下へ様子を見に出てみた。 5つと3つくらいの女の子が、手をつないで立っていた。 姉妹である。小さい子のほうは、顔と胸が焼きただれ、全身がガラスの破片で切れ、血が少しずつ流れている。やけどで、目が見えなくなっている。 姉の方は、いくぶん軽い。顔は、腫れているが、まだ、視野があるのだ。目の見えなくなった妹の手をしっかり握っている。そして、ふたりとも、足が焼けただれて、皮膚がたれ下がっている。 「おかあちゃん、見えないよ」と、小さいほうの子が小さな声で叫ぶ。父も母もいない。 はぐれたのか、すでに死んでしまったのか、姉は妹に答えず、目を精一杯見開いて、まわりをうかがっている。 「地獄だ。人間のできる仕わざではない」 戦う意志が、戸田医師の心に燃えあがった。治療を始めた。 まずいことに、食塩水の湿布が使えない。負傷者たちは、ここへたどりつくまでに、どこかで油をぬってもらっているのだ。油が水溶液を受けつけない。 「ダメだ、どうしよう」 「そうだ、食用油を探してきてもらおう。それから大きな鉢と・・・・」 駆けつけて来た医師たちは、両手で油をすくい、焼けた肌に塗りこんだ。 骨折、内臓露出、全身火傷などの重傷者は、近くの病院に連れこむことにした。 処置の済んだ人は、学校の向かいの神社の境内に、ゴザを敷いて寝かせた。 応援の手が増えてきて、やっと、傷ついた避難民の整理がつきはじめた。 医師たちは、一刻も休むことなく働き続けた。 カトリックの神父がひとり、救援に加わっていた。神父は黒衣をひきずり、処置済みの患者を、なんども、なんども学校から神社まで運んでいった。 神父に背負われた負傷者は、例外なく、ほとんど裸で、腰のまわりに、わずかに布きれが、まとわりついていた。顔や胸やわき腹が焼きただれ、血を流していた。] 目を閉じ、神父の肩に首をのせ、うなだれていた。 神父の黒い衣が、血に染まり、鈍い光沢をはなっていた。 |
|
| ページトップへ | |
| 資 料 名 | 「あのとき閃光を見た 広島の空に」より 昭和59年度 可部町被爆体験記録集 「川のほとりで」 可部町被爆体験継承編集委員会 広島市亀山公民館、広島市可部公民館 |
| 発 行 者 | 広島市教育委員会事務局社会教育部社会教育課 |
| 発行年月 | 昭和61年3月 |